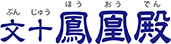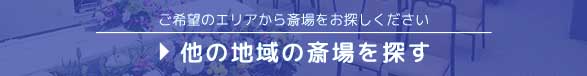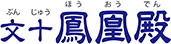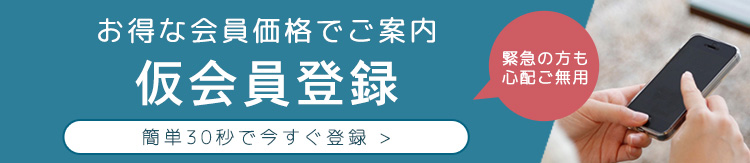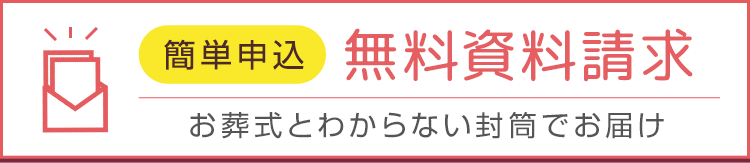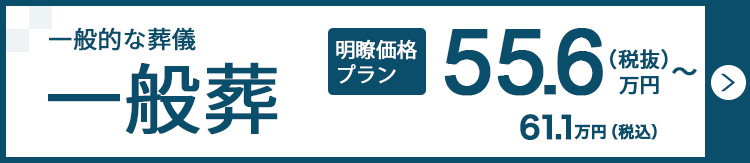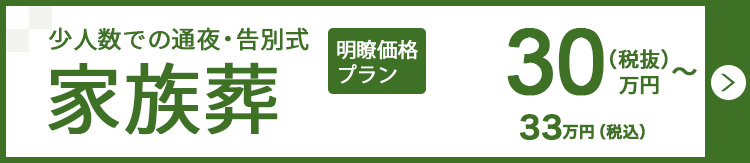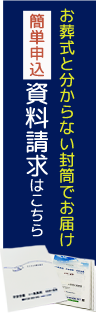平安会館、文十鳳凰殿ブログをご覧いただきありがとうございます。
葬儀場に置いてある「清め塩」。
昨今では使用しない会館も増えているようですが、この清め塩にも込められた意味や正しい使い方があります。
今回はそんな清め塩についてご紹介させていただきます。
「清め塩」とは、死にまつわる“穢れ”を祓うための塩のことを指します。
古くから日本では、塩には清め・浄化の力があるとされ、神事や祭礼などでも使われてきました。
葬儀の場でも故人を偲びながらも“死”を特別なものとして扱う風習の名残として、弔問後に身を清める意味で塩を用いる習慣が広まりました。

清め塩の一般的な使い方をご紹介します。
通夜や葬儀から自宅に戻り、玄関に入る前に使います。
1.肩から胸元、背中、足元にかけて塩をまきます。
血の流れる順番と同じ順番でまくことによって、邪気が血の巡りと共に体に流れ込まないようにという意味があります。
洋服残った塩は家に入る前に払い落としましょう。
2.まいた塩を踏んで建物内に入りましょう。
玄関に入る前に、体に振りかけて払い落とした塩を踏みましょう。
こうすることで完全に邪気を断ち切ることができるとされています。
宗派や地域によっては清め塩を使用しない場合もあります。
例えば、浄土真宗では「死は穢れではない」とされるため用いません。
清め塩の風習は、単なる「決まり事」ではなく、故人との別れを経て、日常の生活に戻るための区切りとしての意味もあります。
別れに悲しみを抱きつつも、残された人々が心と体を整え、また前を向いて日常へ戻るために、一つの手段として根付いた風習なのではないでしょうか。
この清め塩には、そんな優しさが息づいているように思います。
平安会館・文十鳳凰殿
長瀬
平安会館・文十鳳凰殿 公式Instagram・Facebook・Twitterでも葬儀の様子や豆知識などをご紹介しております。
ぜひご覧ください!
◇平安会館
◇文十鳳凰殿